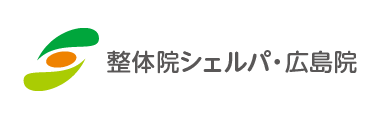
お気軽にご相談ください!


腰や足のしびれや痛みで医師から脊柱管狭窄症と診断され、毎日湿布を貼っている方は多いのではないでしょうか。しかし、いくら湿布を貼り続けても症状が改善しないと感じることはありませんか。実は、多くの患者さんが同じ悩みを抱えています。この記事では、なぜ湿布が脊柱管狭窄症に効きにくいのか、そして本当に必要な治療とは何かについて、臨床経験30年以上の観点からお話しします。


脊柱管狭窄症の患者さんから「毎日湿布を貼っているのに一向に良くならない」というご相談をいただくことが非常に多いです。その理由と対策について、詳しく解説していきたいと思います
湿布は医師の処方や薬局での販売も多いため、脊柱管狭窄症の治療法として一般的に使われています。ただし、実は湿布というのは「対症療法」の一つに過ぎません。つまり、症状を一時的に緩和するための方法であり、根本的な原因を解決するものではないのです。
脊柱管狭窄症は、背骨の中にある神経の通り道(脊柱管)が狭くなり、神経が圧迫されることで腰や足にしびれや痛みが生じる状態です。この狭窄は単純な炎症ではなく、骨の変形や椎間板の変性、靭帯の肥厚などが原因となっています。
湿布には温熱成分や冷感成分、薬効成分が含まれているものもありますが、これらは表面的な痛みを和らげるだけで、脊柱管が狭くなっている本質的な問題を解決することはできないのです。言い換えるなら、火事が起きているのに、火元を消さずに煙だけを消そうとしているようなものです。
多くの人が勘違いしているのですが、脊柱管狭窄症による症状は「炎症」だけが原因ではありません。むしろ、神経そのものが物理的に圧迫されているという構造的な問題が大きいのです。
湿布は炎症を抑えるのには役立ちますが、圧迫そのものを取り除くことはできません。そのため、湿布を何枚貼っても、根本的な改善にはつながりにくいわけです。
また、湿布を長期間使い続けることで、かぶれや皮膚障害が起こることもあります。さらに、湿布に頼り続けると、本来必要な体の修復機能が働きにくくなることも考えられます。
脊柱管狭窄症で病院を受診した場合、通常は以下のような治療が行われます。薬物療法、物理療法、運動療法、そして重症例では手術療法という選択肢があります。それぞれの特徴と限界について見ていきましょう。
痛み止めの薬や湿布は、一時的に症状を緩和する効果があります。しかし、長期使用による胃腸障害や肝機能障害などの副作用リスクがあり、また効果が薄れてきた場合に用量を増やすなど、新たな問題が生じることもあります。
電気治療や温熱療法も対症療法です。確かに一時的には気持ちが良く、痛みが和らいだように感じられます。しかしこれらは症状の根本原因である脊柱管狭窄そのものにアプローチしていないため、治療を受けたその日は良くても、時間が経つと元に戻ってしまいます。
病院で処方される運動療法は、一般的に腰周辺の筋力強化やストレッチに限定されていることが多いです。これも重要な治療法ですが、脊柱管狭窄症の根本原因は腰だけの問題ではなく、全身の骨格バランスや筋力のアンバランスが大きく関係しているため、腰部周囲のみの運動では改善に限界があります。
30年以上の臨床経験から言えることは、脊柱管狭窄症の原因はひとつではなく、複数の要因が複雑に絡み合っているということです。
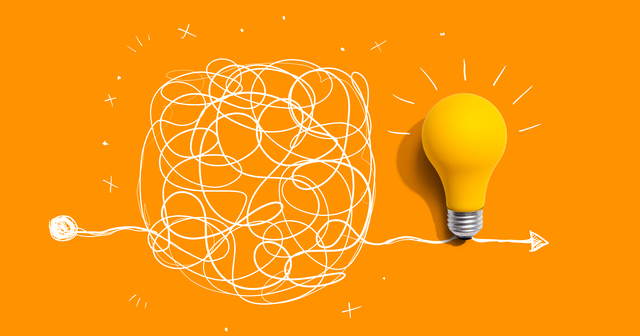
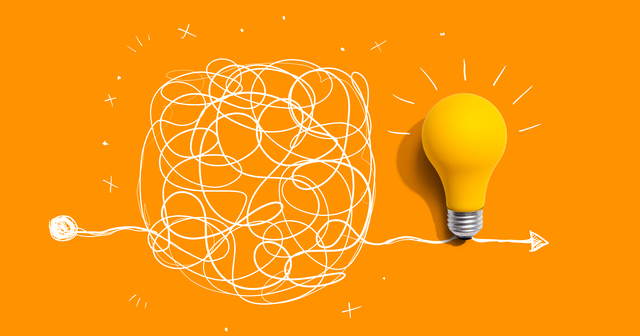
一般的には「加齢による骨の変形」が原因と考えられることが多いですが、実は以下のような要素も大きく影響しています。
これらの要素が何年も積み重なることで、やがて脊柱管が狭窄されるに至るのです。つまり、症状が出た時点では、すでに相当な期間のツケが回っているわけです。
脊柱管狭窄症の患者さんにとって必要な治療は、同じ診断名であっても人によって異なります。なぜなら、その狭窄に至った過程や、現在の体の状態が一人ひとり異なるからです。単に「脊柱管狭窄症だから運動療法」というマニュアル的な対応では、根本改善は難しいのです。
では、脊柱管狭窄症を改善するためには何が必要なのでしょうか。その答えは「徹底した原因特定」と「全身的なアプローチ」にあります。
根本改善を目指すなら、まず自分の体がどのような状態にあるのかを正確に把握することが不可欠です。当院では、足底重心測定器やアライメント検査、筋力検査など、複数の客観的な検査を行い、症状の原因を見つけ出していきます。
単に「脊柱管が狭い」という情報だけでなく、「なぜ狭くなったのか」「どの筋肉が弱っているのか」「どこの骨格が歪んでいるのか」といった個別の問題を明らかにすることが、改善への第一歩となるのです。
脊柱管狭窄症の改善には、狭窄している部分だけをマッサージするのではなく、全身の骨格バランスと筋力バランスを整えることが重要です。足首の動き、股関節の可動域、骨盤の位置、胸郭の柔軟性、そして姿勢のクセまで、すべてが相互に影響し合っているからです。
例えば、足指が使えていない状態が改善されると、歩き方が変わり、それが股関節の使い方に影響を与え、やがて脊椎への負担が減っていくといった連鎖反応が起こります。
検査によって原因が明らかになったら、その人の体の状態に合わせたオーダーメイドの運動療法を実施します。一般的な「腰痛体操」ではなく、その人に必要な筋力強化やストレッチ、動作改善を計画的に進めていくのです。
脊柱管狭窄症で来院された患者さんの多くは、医師から「手術も視野に入れた方が良い」と言われている状態の方です。しかし、適切な検査と治療計画を立てることで、手術を避けて改善に至る例も多くあります。
当院での治療は、初期段階では骨格調整を中心に、狭窄している部分への負担を減らす施術を行います。その後、段階的に筋力強化に移行し、最終的には姿勢や歩行の改善までを目指します。この過程では、患者さん自身もセルフケアやホームエクササイズに積極的に取り組むことが成功のカギとなります。
改善された患者さんからは「最初は200メートル歩くと足がしびれて休まないといけなかったが、今は1キロ以上歩いても大丈夫になった」「旅行に安心して行けるようになった」「階段の上り下りが楽になった」といった喜びの声をいただきます。


脊柱管狭窄症において、湿布は「全く効かない」わけではありません。一時的な痛みの緩和には役立ちます。しかし、それだけに頼っていては根本改善には至らないというのが、多くの臨床経験から見えた現実です。
手術を避けたいというお気持ちもよく分かります。しかし、だからといって湿布と薬だけで何年も過ごすことは、症状の悪化を招く可能性もあります。
大切なのは、自分の体が本当は何を必要としているのかを知ることです。そして、その答えを見つけるためには、徹底した検査と、その人の個別の状況に合わせた治療計画が必要なのです。
脊柱管狭窄症でお悩みなら、一人で悩むことなく、まずは信頼できる治療院に相談してみてください。あなたの体の本当の状態を知ることから、改善への道は始まります。

