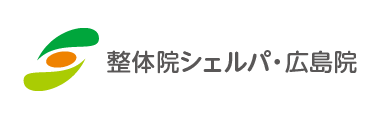
お気軽にご相談ください!


腰から足にかけての痛みやしびれが続いていて、毎日鎮痛剤を手放せなくなっていませんか?特に歩いていると症状が悪化するのに、少し休むと楽になる。そんな経験をされている方は多いと思います。医師に処方された鎮痛剤を飲んでいるのに、なぜか効かなくなってきた。そう悩まれている方のために、今回は脊柱管狭窄症と鎮痛剤についてお話しします。


多くの患者さんが「薬を飲めば治る」と思われていますが、実はそうではありません。薬は症状の緩和には役立ちますが、根本的な原因を解決しているわけではないんです。この違いを理解することが、症状改善への第一歩になります
脊柱管狭窄症による痛みやしびれで悩まれている方は、60代、70代の患者さんが圧倒的に多いです。なぜなら、加齢に伴う骨や靱帯の変性が主な原因だからです。
脊柱管狭窄症というのは、背骨の中を通る脊髄の通り道が狭くなってしまう症状です。加齢に伴い骨が変形したり、椎間板が膨らんだり、靱帯が厚くなったりすることで、脊髄や神経根が圧迫されます。その結果として腰痛、足の痛み、しびれといった症状が現れるわけです。
特に歩いているときに症状が悪化し、立ち止まって少し休むと楽になる「間欠跛行」という独特の症状が現れます。これは脊柱管狭窄症の最も典型的な特徴です。日常生活に大きな支障をきたすため、多くの患者さんが医療機関を訪れ、鎮痛剤を処方されることになります。
ただし、鎮痛剤はあくまで対症療法であり、根本原因を解決しているわけではないということを理解しておくことが非常に大切です。
脊柱管狭窄症の患者さんに処方される鎮痛剤にはいくつかの種類があります。それぞれの特徴と効果を知ることで、自分の症状にどの薬が適しているのか、医師との相談がより実りあるものになるでしょう。
ロキソニンやボルタレンといった非ステロイド性抗炎症薬は、脊柱管狭窄症の治療に最も一般的に処方されます。炎症を抑えることで痛みを緩和するという仕組みです。即効性があり、多くの患者さんが効果を実感しやすいのが特徴です。ただし、長期使用による胃腸障害や肝機能障害といった副作用リスクがあるため注意が必要です。
プレガバリンやデュロキセチンといった神経障害性疼痛薬は、神経自体が過敏になった状態に直接作用します。脊柱管狭窄症による「しびれ」に特に効果的だとされており、多くの患者さんに処方されています。ただし、眠気やふらつきといった副作用が出ることもあります。
硬くなった筋肉を緩めることで症状を緩和する筋弛緩薬も処方されることがあります。特に腰の周囲の筋肉が過度に緊張している場合に効果的です。ただし、これも対症療法に過ぎず、根本解決にはなりません。
多くの患者さんが経験される問題があります。最初は薬を飲んで症状が緩和されるのですが、時間が経つにつれて薬が効かなくなってくるという現象です。これはなぜ起こるのでしょうか。
第一の理由は、鎮痛剤は症状を緩和しているだけであり、根本原因に対処していないということです。脊柱管狭窄症の場合、骨格の歪みや筋肉のアンバランスが複合的に関わっています。薬は痛みという結果にのみ作用しており、その原因である骨格や筋肉の問題は放置されたままなのです。
第二の理由は、症状の原因が単一ではないということです。当院の30年の臨床経験から申し上げると、脊柱管狭窄症の背後には複数の要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。足のアーチの機能低下、股関節の可動域制限、骨盤の歪み、さらには姿勢や日常生活動作の問題など、多角的な要因が関係しています。薬はこうした複合的な問題に対応することはできません。
加えて、痛みをかばう姿勢を続けることで、さらに筋肉のアンバランスが進んでしまいます。この悪循環に陥ると、症状は一層複雑になり、薬の効果も薄れていくわけです。
病院では一般的に薬物療法と運動療法が組み合わせられます。これ自体は悪くない考え方ですが、実際にはその効果は限定的です。なぜなら、病院で処方される運動療法は腰部周囲に限定されることがほとんどだからです。
脊柱管狭窄症を根本から改善するためには、全身の筋肉のバランスを修正する必要があります。足底のアーチから始まり、下肢全体、骨盤、腰椎、胸郭、そして上半身に至るまで、全身的なアプローチが欠かせません。そこまでできる運動療法は、残念ながら一般的な病院では提供されていないのが実情です。
「処方薬ではなく市販薬で対応できないか」とお考えになる患者さんもいらっしゃるでしょう。市販の鎮痛剤も、病院で処方されるものと同じようにNSAIDsが主体です。一時的な痛み緩和には役立つかもしれません。
ただし、脊柱管狭窄症のように慢性的な症状については、医師の診断と指導のもとで適切な薬を処方されることをお勧めします。症状の程度や個人の体質によって最適な薬は異なります。また、他の疾患や服用中の薬との相互作用も考慮する必要があるからです。市販薬に頼ることで、かえって症状を複雑にしてしまう可能性もあります。
長期間の鎮痛剤使用には、避けて通ることができない副作用のリスクがあります。NSAIDsの長期使用による胃腸障害は特に注意が必要です。胃痛や不快感だけでなく、消化性潰瘍に至ることもあります。
神経障害性疼痛薬には眠気、ふらつき、体重増加といった副作用があります。特に高齢者の場合、ふらつきは転倒のリスクを高めます。転倒による骨折は、その後の生活の質を大きく低下させる可能性があります。
さらに注視すべき点は、これらの副作用が生活習慣に悪影響を与えるということです。眠気やふらつきのために外出や運動を控えるようになります。その結果、筋力が低下し、かえって脊柱管狭窄症の症状が悪化するという悪循環に陥るわけです。
脊柱管狭窄症から根本的に解放されるためには、何が必要でしょうか。答えは明確です。症状の根本原因を特定することです。
原因がわからないまま治療を進めることは、コンパスを持たずに山に登るようなものです。方向性が定まらないまま歩き続けても、山頂には到達できません。脊柱管狭窄症についても、全く同じことが言えます。
丁寧なカウンセリングと徹底した検査で原因を明らかにすること。これが改善への第一歩になります。足底重心測定器をはじめとする複数の検査により、なぜ今痛みが出ているのか、その本当の理由を見つけ出す必要があります。
薬が必要ないということではありません。急性期の痛みを緩和するために、鎮痛剤は一定の役割を果たします。ただし、薬だけに頼るのではなく、適切な検査のもとに原因を特定し、その原因に対する根本的なアプローチを並行して進める必要があります。
当院では、このような視点から脊柱管狭窄症の改善に取り組んでいます。最新の身体理論をベースとした独自の検査で原因を特定し、骨格を整え、筋肉のバランスを修正し、姿勢や動作を改善していく。運動力学に基づくこのアプローチは、薬では対応できない部分を補完する重要な役割を果たします。
当院で施術を受けられた患者さんたちは、どのような変化を経験されているでしょうか。その一例をご紹介します。痛み止めを毎日飲むことが当たり前だった方が、やがて飲む頻度を減らすことができるようになります。薬に頼らなくても生活できるようになった、という報告も多くいただきます。
症状が緩和されるだけでなく、歩く距離が伸びたり、以前はできなかった動作ができるようになったり、そして何より痛みを気にせず生活できるようになった。こうした改善は、根本原因に対する適切なアプローチがあってこそ実現するのです。
脊柱管狭窄症で悩まれている方の多くが、「これは年のせいだからしょうがない」「手術しかない」と考えてしまいます。確かに加齢は関係しています。しかし、年だからこそ改善できることがたくさんあるのです。30年以上の臨床経験の中で、私たちは多くの高齢患者さんの症状改善を見守ってきました。
あなたの脊柱管狭窄症は、もしかしたら単なる「加齢による変化」ではなく、改善可能な問題かもしれません。薬だけに頼らず、根本的な原因に向き合うことで、新しい可能性が開かれることがあります。一人で悩むことなく、いつでもお気軽にご相談ください。あなたの状態を詳しく検査した上で、最適なアプローチをご提案します。

