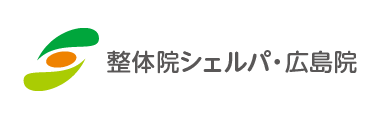
お気軽にご相談ください!


腰部に痛みを感じたり、足のしびれが出たりするのは本当に辛いですね。その症状は、もしかして脊柱管狭窄症かもしれません。医学の検査で診断を受けた方も、まだ診断前の方も、症状と向き合うなかで「何か自分でできることはないだろうか」と考えるのは自然なことです。実は、食事の工夫が脊柱管狭窄症の症状管理に大きな役割を果たすことをご存知でしょうか。今回は、症状の改善をサポートする食べ物と栄養について、臨床経験に基づいてお伝えします。


脊柱管狭窄症でお悩みの患者さんから「何を食べたら症状が楽になるのか」というご質問をよくいただきます。食事療法だけで症状が完全に治ることはありませんが、体の内側から改善を支えることで、施術の効果をさらに引き出すことができるんです
脊柱管狭窄症の症状を抱える患者さんの多くが、「症状をなんとか和らげたい」という想いを持ちながら、医師や整体師に相談することをためらっています。なぜなら「この症状は手術しか治らない」「加齢だから仕方ない」といった説明を受けることが少なくないからです。しかし30年の臨床経験から言えることは、適切な食事管理と体の使い方の改善により、多くの症状を緩和することができるということです。食事というのは毎日3食、毎日あなたの体に栄養を届けるシステムです。その栄養が不足していたり、炎症を促進するような食べ物ばかり摂取していたりすれば、体は当然のことながら回復に向かいません。
脊柱管狭窄症の主な原因は、加齢に伴う脊椎の変性です。それに加えて、仕事でのデスクワークによる長時間の同じ姿勢、筋肉の衰退、体の歪みなど、複数の要因が重なることがほとんどです。そしてこれらの要因に共通しているのが、骨の健康度や筋肉の質が大きく影響しているということです。食事を通じて、骨を支える栄養と炎症を抑える栄養を意識的に取り入れることは、脊柱管狭窄症の症状管理において非常に有効な手段になります。
食事療法というと、何か難しい専門的なことをしなければならないと感じるかもしれません。しかし実際には、いくつかのポイントを意識するだけで、日常の食事を症状改善に役立つものへと変えることができます。脊柱管狭窄症の患者さんに必要な栄養管理の基本を整理してみましょう。
脊柱管狭窄症では、脊椎の骨が変形し、脊髄や神経根が圧迫されている状態です。この状態を改善するためには、骨の質を高め、神経周辺の炎症を抑える栄養が必要になります。具体的には、カルシウム、ビタミンD、ビタミンK、そしてタンパク質が中心的な役割を果たします。カルシウムだけを摂取していても、ビタミンDがなければ吸収されません。単一の栄養素ではなく、それらが協力し合う環境を作ることが大切です。
脊柱管狭窄症の痛みやしびれは、神経圧迫だけではなく、周辺の炎症によって増幅されることがあります。そのため、体の炎症を助長する食べ物を避け、炎症を抑える食べ物を意識的に選ぶことが重要です。オメガ3脂肪酸を含む食品や、抗酸化物質を豊富に含む野菜・果物が有効です。
肥満も脊柱管狭窄症を悪化させる大きな要因です。体重が増えれば、脊椎への負荷が高まり、症状が出やすくなります。カロリー管理と栄養バランスの両立が、長期的な症状改善の鍵になることを忘れないでください。
では、実際にどんな食べ物を選べばいいのでしょうか。脊柱管狭窄症の症状を抱える患者さんにとって有効な食べ物を、栄養別に紹介します。
牛乳やヨーグルト、チーズなどの乳製品はカルシウムの宝庫です。ただし、脂質が多いタイプを選ぶと、カロリーオーバーになってしまいます。低脂肪乳や無糖ヨーグルトを選ぶことをおすすめします。小魚、特にイワシやシラスには、カルシウムとビタミンDが一緒に含まれています。週に2~3回、小魚を食べることを習慣にすると効果的です。
納豆も脊柱管狭窄症の患者さんに非常に有効な食べ物です。納豆に含まれるビタミンKは、骨の形成と維持に不可欠な栄養素です。毎日1パックの納豆を食べることは、骨の健康を守るうえで非常に価値があります。青菜類、特に小松菜やほうれん草にもカルシウムとビタミンKが豊富に含まれています。
脊柱管狭窄症の患者さんの多くが、加齢に伴う筋肉の衰退によって症状が進行しています。筋肉を維持・強化するためには、質の良いタンパク質を毎食摂取することが必要です。鶏肉の胸肉、豚肉のロース、鮭などの白身魚は、低脂肪で良質なタンパク質を含んでいます。大豆製品(豆腐、味噌、豆乳)も、植物性の優れたタンパク質源です。
卵も完全栄養食として知られています。朝食に卵を1~2個食べることで、1日を通じた良質なタンパク質摂取の基盤ができます。無理に動物性タンパク質だけに頼らず、植物性と動物性のタンパク質をバランスよく組み合わせることが大切です。
脂の多い魚、特に鮭やマグロ、イワシなどに豊富に含まれるオメガ3脂肪酸は、体の炎症を抑える働きがあります。週に2~3回、これらの魚を食べることをおすすめします。オリーブオイルにもオメガ3が含まれており、サラダに少量かけるだけでも効果があります。
トマト、ブルーベリー、ナッツ類には、抗酸化物質であるポリフェノールやビタミンEが豊富です。これらの食べ物は、神経周辺の炎症を穏やかにし、神経障害の進行を緩和するのに役立ちます。毎日の食事に、色彩豊かな野菜と果物を取り入れる習慣をつけましょう。
症状改善に役立つ食べ物があれば、反対に避けた方がいい食べ物もあります。これらを把握することは、症状改善のためと同じくらい重要です。
揚げ物やスナック菓子、加工食品に含まれるトランス脂肪酸や酸化した油は、体の炎症を促進します。これらを頻繁に摂取していれば、せっかく他の食べ物で摂取した抗炎症物質の効果が相殺されてしまいます。完全に避ける必要はありませんが、週に1~2回に限定することをおすすめします。
砂糖をたっぷり含むお菓子やジュースも、炎症を促進し、同時に体重増加をもたらします。脊柱管狭窄症の患者さんにとって、体重管理は症状管理の基本中の基本です。清涼飲料水を常飲している習慣があれば、今すぐ改めることをおすすめします。
夜遅い時間の食事、特に就寝の2~3時間以内の食事は、消化器官に負荷をかけ、睡眠の質を低下させます。脊柱管狭窄症の症状は、夜間痛が強い患者さんも多いため、質の良い睡眠を確保することは非常に大切です。就寝時間から逆算して、少なくとも2時間前には食事を終えるよう心がけましょう。
また、一日の中で栄養摂取が夜に偏るのも避けるべき習慣です。朝食を抜いたり、簡単に済ませたりしている患者さんは少なくありません。朝、昼、晩のバランスの取れた食事リズムが、体の回復能力を最大限に高めるのです。
ここまで、脊柱管狭窄症に有効な食べ物と栄養について説明してきました。しかし、食事療法だけでは十分ではありません。私の臨床経験からいえることは、食事管理と適切な施術・運動療法の組み合わせが、最も高い改善効果をもたらすということです。
食事は、体の内側から必要な栄養を届け、炎症を抑え、骨と筋肉の健康度を高めます。これは、症状改善の「環境整備」ともいえます。一方、施術は、脊椎の歪みを正し、神経圧迫を軽減し、姿勢と動作を改善します。これは「構造の改善」です。環境整備と構造改善の両方が揃って初めて、根本的な症状改善が実現するのです。
多くの患者さんは、「食事だけで治るか」または「施術だけで治るか」と、どちらか一方を求めようとします。しかし実際には、両者は相互補完的な関係にあります。栄養が十分でなければ、施術の効果も半減します。逆に、構造が改善されなければ、栄養摂取の効果も限定的です。
当院では、患者さんに食事管理のアドバイスをしています。その結果、食事に気をつけ始めた患者さんの多くが、より早く症状の改善を実感しています。「食べ物を意識するようになってから、朝の痛みが減った」「栄養を気にして体重が減ったら、歩きやすくなった」といった声をよくお聞きします。
脊柱管狭窄症は、診断を受けたからといって、その瞬間から急速に悪化するわけではありません。その一方で、何もしなければ、確実に進行していく傾向があります。この事実を前にしたとき、患者さんにできることはいくつもあります。
まずは、食事を見直すことから始めましょう。特に、朝食の充実、夜遅い食事の改善、そして毎日の栄養バランスへの意識。これらは、新しく何かを追加する必要がなく、今の習慣の中での改善なので、今日から始めることができます。同時に、運動習慣の定着と、必要に応じて施術による構造改善も重要です。
脊柱管狭窄症で悩みながらも、「自分でできることはないか」と考え、食事の工夫や体の使い方の改善に取り組む患者さんの多くが、確実に症状の改善を実現しています。症状がつらいからこそ、その瞬間瞬間は大変かもしれません。しかし、その先には、痛みのない日々、自分がやりたいことを思う存分できる人生が待っています。
一人で悩まずに、どんなことでも構いませんので、いつでもご相談ください。あなたの症状改善に向けて、食事管理の側面からも、施術の側面からも、全力でサポートします。

